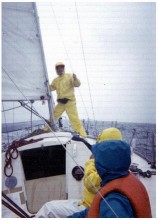また、モットー(motto)とは行動や努力の目標とする事柄ですから、日本の商船学校系出身者はシーマンシップと聞けば、10人中9人はこれに似た上記の言葉を口にするのではないでしょうか。 シーマンシップを好んで多用し大目標としているのは、ヨットマンですね。「シーマンシップは精神論ではない、船を安全に航海させる知識・技術」と位置付けているようです。実際、英和辞典を引きましても、 seamanship → 操船術 と、書いてあり間違いありませんが、 ただ、ヨットマンが精神論ではないと断言する根拠が見つかりません。 そもそも ○○○ship とは、名詞・形容詞に添えて次の意味を表す。
シーマンシップを説明する際にスーポーツマン精神(スポーツを通じて養われる総合的人格や技術)と訳されることの多い sportsmanship を例に取り、元々 ○○○ship に精神という意味はないとして、シーマンシップと船乗り魂は違うのだと 逆否定する文献もありますが、私は賛同しかねます。 英語は状況に応じ意訳して構わないからです。 ていうか、素直にSportsmanshipを辞書を調べますと、小学館の英和辞典PROGRESSIVEには、「スポーツマン精神、正々堂々とした態度」とあり、角川さんの国語辞典には、「正々堂々と競技の勝負を争う精神」と書いているのです。この論法のおかしいことがわかる。
外国人の船乗りに seamanship の意味を単に聞くと、ヨットマンと同様「船乗りとしての トータル的な技術・能力」と答えるかも知れませんが、必要に応じた技術を論じる場合、現実的に ○○○ship を 知識や技量と訳すのには、やや問題があるように思います。漠然として意図する意味が伝わりにくい。技量は skill 、技術は technique、知識は knowlege、能力は ability と言うのが一般的ですし、わかりやすい。 操船術や航海術を seamanship などと言えば間違いなく誤解が生じます。 操船術は ・・・・・・・ 航海術は ・・・・・・・ と言わないと通じません。 私はヨットの知識・技術・モラルを総称し yachtsmanship と呼ぶことについて全く否定しませんけれど、ヨットも商船も漁船も軍艦も外国船も同次元で考えて、一括りに 「seamanship はこうだ」等と言うのは、 少々こじつけ気味に聞こえ、無理があるように思います。 船乗り(ほんとの意味でのseaman)に関して言えば、知識・技術のない者はもともとプロになれませんから…。原点が異なります。 冒頭申しました「船乗り気質」は、(昔は)多くの船乗りがもち合わせていた。逆にこれを英語に直すとすればなんと言うのですか? それこそ「SEAMANSHIP」がぴったり嵌ると、私は思います。 (日本)商船での、seamanship なる摩訶不思議な言葉は、結論的に精神論と片付けた方がどうも自然のような気がします。 ちなみに 空の airmanship や 山の mountaineership (alpinistship かな?)などもやはり技術面を総括した言葉なんでしょうか???
|
||||||||||
| 「船の不思議」の続きは、こちらから | ||||||||||
上記の内容をフルスペックでご覧になりたい方は以下にてお願いします↓ |
||||||||||
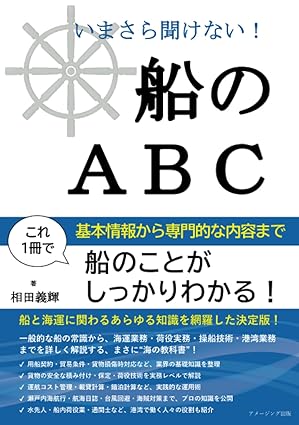 |
||||||||||