| 曳航力 実証値に裏付けされた文献等によると、曳船の曳航馬力と曳航力(索張力)の関係は・・kn’t以下の速力で・・・馬力に対して約・・・・t程度と考えられている。 一般に曳航限界荷重は索具(ロープ)破断荷重の・・倍(安全率・・)を理想としているが、作業性や経済性を考慮し現場では・・・・・・倍を採用することが多いようだ。 ある会社を例にとると、タグボートα丸の曳航力は・・・t、Ropeの径はφ・・・・mmとしています。これをポリエチレン製とした場合の破断力は・・・tですから、安全率は・・・ということになる。曳航索は安全率・・以上での使用を推奨し、・・以下で曳航不能であるから、穏やかな港内で本船離着岸の速力を抑えた上、減速・増速・制動作業を行うなどして問題がない。 また、この曳航力は常時発揮されて業務されているものではないことを以下に検証する。 |
||||||||||||||||
| ①たとえば、5kn’tで惰力航行中の排水トン100,000の船を曳き船で後方に引かせ進出距離5cableで停止させる場合の曳航力と停止までの経過時間を計算する。風潮及び船体抵抗などにより曳航力は15%損失があるものとするとした。 運動エネルギーと曳航エネルギーは等しいので、 (V2-Vo2)W/2 = F(1-a)gL 運動量変化と力積の関係から W(V-Vo) = F(1-a)gT |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| F = (・・・・・・・・・・・・) / ・・・・・・・・・・・・・・ = (・・・・・・・・・) / ・・・・・・・・
= ・・・t T = (・・・・・(・・・・)) / ・・・・・・・・・・ = (・・・・・・・・・・) / ・・・・・ =・・・・・秒 = ・・・分 |
||||||||||||||||
| ②次に5kn’tで航行中の排水トン1,100(Laden)の艀を曳き船で後方に引かせ進出距離50mで停止させる場合の曳航力と停止までの経過時間を同様に計算する。風潮及び船体抵抗などにより曳航力は15%損失があるものとするとした。 F = (・・・・・・・・・・) / ・・・・・・・・・・・・・・ = (・・・・・・・・・) / ・・・・・・・・ = ・・・t T = (・・・・・(・・・・)) / ・・・・・・・・・・ = (・・・・・・・・・・) / ・・・・・ =・・・・・秒 (この計算は・・・航行中から・・・までを計算したが、・・・したものをその・・・まで・・・させるのも同じことである。) |
||||||||||||||||
| 艀の曳航力に加わる風潮などの影響は、 風圧力 (t) = 1/2 ρa・Ca (Acos2 θ + Bsin2 θ) Va2
|
||||||||||||||||
となるので、航行可能な・・・m/s以下での加算風圧力は、
|
||||||||||||||||
| これを上記、F=・・・t に加えた・・・tが索張力と考えられる。 従って、曳航索の安全率を・・倍とした場合には、・・・・・・・・・ = ・・・tの破断力を備えたものを用意する。安全率・・とした場合には、・・・・tの破断力が必要である。 曳船速度が・・・kn’t以上で索張力は著しく・・・・・・・・・・するとされているので、巡航速度に注意を要する。 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
| 曳航索選定顛末是非 1000t艀曳きの現場で、ポリエチレン製50mm径(Material Breaking Strength 355kN≒36.2tの新品)が、爆弾低気圧下の航行に於いて・・・・・に遭遇して切断した事故や、同・・・mm(材質、破断強度、経年数不明)破断事故、または、友ヶ島外における大型船の引き波による大きな振れ回り現象など、経験則による例を挙げて、より大きな径の曳航索を要求があったという。 ここで特筆すべきは、前述の50mm径の事故である。索具が新品であったことから経年劣化は考慮されず、この際は単に・・・t程度以上の張力が加わって曳航索が切断されたことになる。計算を上回る数字です。(・・・・・での上下運動によって・・・・・・・が・・・倍になるのかも知れない。)但し、正確な数字はわからない。 運航基準の定めがしっかりしておらず、・・・・・・・・・・を船長のみに委ねていたため、船廻しを憂慮して無理をされる場合もあったとのことで、安全第一の観点から現場の意見を尊重する。荒天下の曳航索の最大張力を・・・t以上と仮定することとした。 設備(ドラム型ウインチがない)上、大径索では作業上(人力)の困難が生じるため、艀A丸には破断まで幾何かの余裕をもって対抗でき得る・・・mm(B.S.・・t)の曳航索としたが、・・・曳きの際に先艀となることが多く、荒天時のシャクリが大きい艀B丸には・・・mm(B.S.・・・t)を支給したという。 安全率として過大か妥当か? これらの状況は、機会が少ない海象も想定し、索具を選定しているので一見、安全に重きを置いているように思えるが、・・・・・・・・・・がともに損なわれている感を否めない。作業性の悪化は・・・・・・・・の低下を生み、また、高価な索具を購入は、その代替時期が伸びる傾向になる。それは結果的に経年劣化を進めて強度を半減させますから、やはり事故の原因につながります。索具の定期的な代替は安全に大きく寄与する。 上記、艀B丸には・・・mmを支給することとしたようだが、これが荒天下で再び切断することとなった場合、現場からは・・・mmまたは・・・mmという声が必ず上がります。怖いから当然であるが、キリがない。 一般的には、・・・・・・・や・・・・・・・・が設定され、運航を実施します。そのうえで、荒天予想時に事務所の・・・・・・・・・・・・が船長と発航中止を協議または指示することによって、上記の危険等は回避されます。「・・・5mmが切れるよう荒天時に船は出さない」(三角波など論外!艀などは波高・・・mが限界かと私は思う)というようなことを厳守する。そして、これを曳船船長・艀作業員にしっかり安全教育を施し、理解を求めることが最も重要である。 安全率を如何にして曳航索を支給すべきか、運航管理すべきかが大きな課題と言えます。使用条件を整え(運航基準・定期代替)て、適切な使用曳航索が選定されるよう期待します。(または、・・・・mmを限度にして、逆に・・・・・から・・・・・・を設定してもよい) |
||||||||||||||||
| 曳航索の安全率を保つための操船要領 ①設備している曳航索の強度は、その安全性、作業性、経済性を考慮し、曳航力(索張力)の・・・倍以上の・・・・をもって定めるのが通常だが、速力・・・kn’t以下での曳航力(索張力)を・・・・馬力につき約・・tとして計算したもので、あらゆる条件下で一定したものとなりません。 一般的に造波抵抗・摩擦抵抗等は・・kn’tを境に急激に増加します。これにより索張力は・・・・馬力につき・・・t以上となっていくため、安全率は・・・・以下まで減少していきます。 ②・・・・によって安全率が・・以下になると、ロープはいつ破断してもよい状態に陥ります。通常曳航索は安全率・・以上をキープして使用されることが望ましく、船長は①及び②、積荷の量などを鑑み、・・・・・・・・を避けることのできる安全な速力を決定しなければならない。 ③風浪の影響は、・・・%マージンとして設定しています。これは風速・・・m&波高・・mを想定して安全率を計算しています。条件が悪化すれば、安全率は下がります。 ④・・・・や・・・・の影響によって・・・、振れ回りなどの現象が現れた場合にも、索張力は上昇し安全率は減少しますので、直ちに減速することを考慮しなければならない。但し、・・・・・・・・速度は保たなければならない。 ⑤巡航速度に達しようとする・・・、または、停止させようとする・・・が・・・ほど、索張力は増します。船長は急激な・・・、・・・を避け、周辺の状況を考慮しつつできる限り・・・・・・・・・・巡航速度への到達を目指し、または、前以て十分な・・・・・・・・・・作業に入ることを心掛ける。 ⑥・・・・・・・・の傷み、・・・・・・切れ、局部的な負荷などによっても索具の強度は保たれない。曳航時は隔時観察を施し、必要に応じて・・・・・・や、索具の調整などを施す処置を行う。また、・・・・・・以下であっても経年劣化が進んだものについては交換の対象となる。 |
||||||||||||||||
上記の内容をフルスペックでご覧になりたい方は以下にてお願いします↓ |
||||||||||||||||
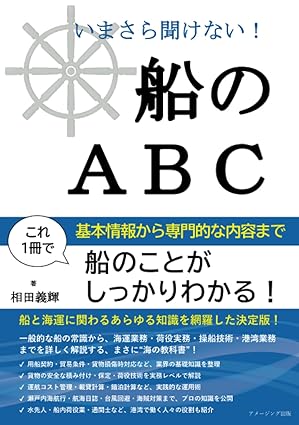 |
||||||||||||||||