| 鋼材や穀物などの海上運送で絶対に忘れてならないのが結露(Condensation)である。結露は鋼材の錆や、穀物のカビなど貨物のダメージにつながります。 「鹿島(茨城県)より南で積んだ鋼材に結露は起こらない。」 と、某有名大手内航船社の海務の方が言っているのを耳にした。結露の南限が鹿島とは非常に興味深い説です。根拠が気になったので耳をそばだててさらに聞いていた。 「夏に冷蔵庫から冷えたビールを出すと瓶に水滴が付く。あれが結露だ・・・」 などと、真顔で部下に説明している。。。たから、困り顔の部下の代わりに言いますが、 「そんなことは知っている。」 部下が知りたいのも私が聞きたいのも、なぜ結露が起こるかなのだが、核心には触れてくれなかった。 なので、代わって解説する。 水蒸気を含む空気(通常の空気)の中に置かれた金属を冷やしていくと、金属の表面に露(結露)が付き始める。その時の金属の表面温度を露点温度(Dew point)というが、周囲の露点温度より金属の温度が低いとき結露する。 湿度が高くなると、露点温度も高くなるので、その中にある金属が一定温度でも結露しやすくなるというわけです。以下に例を示す。 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| * 露点温度を求める公式や、湿り空気線図もあるが、温度と湿度によって表(露天温度表)から求めるのが簡単でよい。 | |||||||||||||||||||||
積荷前のCoil(結露が特に問題となる貨物)は・・・・・・・・・・内に収められているか、もしくは(短期的に)・・・・・・・・野積みされていたりもする。冬場、西日本の平均気温でも・・・℃~・・・℃くらいなので、これらCoil等鋼材を積んで南方へ下ると、以下のようなメカニズムで結露の発生につながる。 ① 船が日本を出港し、南に下ると・・・日もすれば、外気は高温多湿となる。 温度4.0℃ 湿度78% / 露天温度1.7℃ Coil表面温度2.0℃ ② 艙内環境は温度(・・・・・作用する)・湿度(・・・・・等の影響)ともに上昇してゆく。 出港後2日 温度・・・℃ 湿度・・・% / 露天温度・・・℃ Coil温度・・・℃ ③ 艙内温度が・・・・・、Coilの・・・・・・・・が、艙内環境は温度・湿度ともに日々変動するので、Coilの温度が・・・・・・・・・・・・回ったとき発汗(結露)する。 出港後7日: 温度・・・℃ 湿度・・・% / 露天温度・・・℃ Coil温度・・・℃(発汗) |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
同温では・・・・・・・・・・ほど露天温度も高くなることは説明したが、よく誤解されるのが、単に「Hold 内の・・・・が外・・・・・・・・より高い場合」にベンチレーションする」ということだ。 例えば、Coilの表面温度が・・・℃のとき、 Hold内温度 ・・・℃ 湿度90% = 露点温度・・・℃ で、発汗が始まったとしよう。 外気 温度 ・・・℃ 湿度80% = 露点温度・・・℃ なら湿度は・・・・より低いが、・・・を入れてはならない。・・・・の湿度が・・・・ 内のそれを下回っていても露点温度が・・・・より高く、ベンチレーションすればHold 内でCoilにさらにひどく結露する。 次に温度に関し説明しよう。冷蔵庫のビールを何がし(上記)で示したように冷えたものを温度の・・・・・空気に触れさせると結露するという誤解も危険だ。例えば、船倉内でCoilが18℃だったとき Hold内 乾球・・・℃ 湿球・・・℃ (湿度・・・%) 露点温度18.5℃ で、結露が始まったとする。 外気 乾球・・・℃ 湿球・・・℃ (湿度 ・・・%) 露点温度17.0℃ なら外気の方が温度が・・く、上記に関連しベンチレーションすればいかにも結露するように思われる。しかしながら、この場合・・・を入れても理論上結露・・・。Coilの温度が外気の露点温度より・・いからである。(まず海上では乾球&湿球の差がこのような状態にはならないでしょうけど) 兎に角、このようにベンチレーションは温度とか湿度とか一方で決めてはいけない。 結露防止に最も有効なのは、Heater Unit + Dehumidifier(除湿機)を使用し、船倉内を密閉して・・・・・の・・・した空気を循環させることです。例えば、船倉内温度を・・℃まで上げ、湿度を・・%ぐらいまで・・・げることに成功した場合、露点温度は25℃となる。このときCoilの温度は・・℃(通常Coilの表面温度は艙内温度より少なくとも・・・℃低い)ぐらいになるので、結露は付かない。 (除湿機を設置し、上記のようにすれば確かに航海中は結露しない状態を維持しやすい。ただし、忘れがちなのは、揚地に到着して・・・・・・・・・・・・・・・・・、やはり結露する。十分に・・・・・・・・・・が上がっていなければならない。航海中のせっかくの努力を水の泡にしないようにして下さい。)しかし、Dehumidifierの最大の欠点は・・・・・・・・・・がいるということだ。船にこのような機械を設置するのは・・・・・・・・・・。 では除湿機がない船は、どういう対処がよいかという話になる。(ほとんどの船がこれ) 結論から言えば、・・・・・・・・・・の温度も上昇するが、これに伴いCoilの温度も徐々に上昇するので、・・・・・・・・・したまま航海する方がよい。 1)Coilの表面温度は、周辺温度(乾球温度)より少なくとも・・℃低い。(実証実験結果より)Coilの表面温度を測定することは通常不可能であるため、これにより推測する。 2)通常「・・・・・露点温度 > ・・・・・露点温度」の場合(冬場に日本から南下する場合はなかなかこういうコンデションにならない)は、ベンチレーションを回し外気を取り入れてよい条件とされるが、Coil(金属)表面温度が外気露点温度より・・・・・回る場合は、「・・・・・露点温度 > ・・・・・露点温度」であっても、・・・を流入させれば発汗するので注意せねばならない。 3)その目安は、 周辺温度・・ - ・・・℃のとき、 ・湿度・・・%の条件で、露点温度は、そのときの乾球温度より・・・ - ・・・℃低くなる。 (この場合はCoilの表面温度の方が更に・・・いので、既に・・・状態であると言える。これには乾燥・除湿装置で対応する以外としては、・・・・・し・・・・・でwipe upしつつ、 Coil温度が・・・するのを待つ他に手段がない。) ・湿度・・・%の条件で、露点温度は、そのときの乾球温度より・・・ - ・・・℃低くなる。 これらを総合的に考慮すれば、航海途路Hold内は湿度が・・・%を超すことが常であるため、実測できない場合は、より温度の低いCoil表面温度を採用(想定)し、それと・・・の・・・・・を比較して・・・・・・・・・の可否を決定すべきものである。 よくわかってない荷主などからは 「徐々に外気を入れてHold 内を揚地の状況に近づけていったらどうか?」 などの意見がある。外気の・・・・・・・・・・場合は、騙し騙し入れても必ず結露する。航海中に日々結露させるか、・・・・・・・に結露させるかの違いだけで、結果は同じである。(船会社の立場から言えば、・・・・・の方が責任上ベターと言えなくもない。)なので今のところ、機を逃さず外気の・・・・・・・・・・回るときを選んで積極的に・・・・・することが、Total 的に結露を・・・・・・・・・・ることのできる最良措置と言えます。 具体的には、冬の航海で艙内の・・・・・・・・・・く、外気の・・・・・・・・・・状態が継続して南半球(インドネシア等)まで到着することが多いので・・・・・・・・・・ない方がよく、夏場は・・・・・・・・・・・・・・・が度々生じる。 さらに夏場の南半球でバルクカーゴを・・・・・・・・・して貨物が・・・・・場合も結露の危険がある。結露は冬場だけではない。温かいところから・・・・・・・・結露は起こるのです。 タッパーにはいった温かいご飯を冷蔵庫に入れるとどうなるだろうか? タッパー内に水滴が大量に付着します。タッパー内で・・・・・・・・・・・・・・・・・が始まったからです。つまり結露ですね。そう、タッパーが船で、冷蔵庫内が北上した冷たい海です。 船倉の中にある・・・・・・・・・・空気は、北上する過程で冷やされていく・・・・・や・・・・・に結露します。 艙内(貨物)温度が・・・℃で湿度が・・・%でしたら、・・・℃が露点温度になります。海水温が・・・℃以下などの海域を航行すれば外板は・・・℃より下がる可能性があるので要注意です。 ここまで説明すれば、もう冒頭のビール瓶の話を深く理解できるのではないでしょうか? ビンはあたかも温度だけに作用して結露したように見えるが、実は・・・・・・・・・・されている。仮に、ビールを美味しい温度の・・℃に冷やしたとして、冷蔵庫から出してみる。部屋の温度が・・・℃ならビール瓶に・・・するのが当然だが、もし(再度、仮に)その部屋の湿度を・・・%にすることができれば、露点温度は・・・℃となるので、・・・℃の瓶に結露はしないですね。どうですか?納得できましたか? |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
上記の内容をフルスペックでご覧になりたい方は以下にてお願いします↓ |
|||||||||||||||||||||
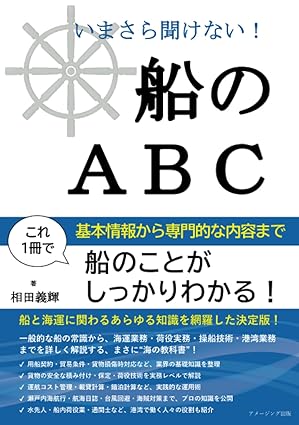 |
|||||||||||||||||||||
