| 発達した低気圧や、台風が接近する場合、各港の港長は警戒(避難)体制を発令する。 それらの発令時期や、指針や措置は、港の特徴(地形、影響の受けやすさ等)によって異なるが、大まかに共通する部分とそうでない部分があるので参考にされたい。 第一警戒体制 どこの港も共通して荒天準備と考えてよい。 発令時期基準 地方港では、強風域(風速・・・m/s以上)に入ると予想される数時間前というのが、一般的のようだ。 徳山:・・・域に入ると予想される・・時間前までに行う。 鹿島:・・・域に入ると予想される・・ 時間前。 金沢:・・・の・・・・・域が・・・時間以内に到達されると予想される場合。 などだが、大阪港は、台風の・・・域に入るおそれがあると判断された場合、千葉港は・・・域が達するまでに荒天準備が完了することを目安に発令する。など、時間によらず漠然としたものになっている。 講ずべき措置 概ね、 1)台風等の動向に留意し、荒天準備をなし、必要に応じて運航できるよう準備する。 2)荷役中の船舶は、・・・・・・・・・・出来るように準備する。 3)VHFの聴取 だが、大阪港では原則として・・万t以上の港外退避。・・・・・t以上の入港見合わせ。金沢などでは、第一警戒体制であっても・・・・・の船舶は・・・し安全な・・・・・・・・・・(・・・は沿岸から・・・mile外)すること。など、より厳しいことを求める港もある。 第二警戒体制 これは・・・・・と位置付けられる。 発令時期 地方港では暴風域(風速・・m/s以上)にかかると予想される・・時間前の発令が多い。 徳山:・・・域に入ると予想される時刻の・・時間前までに行う。 鹿島:当港が・・・域に入ると予想される・・ 時間前。 金沢:台風の・・・・・域が・・時間以内に到達されると予想される場合。 だが、阪神港(大阪区、堺泉北区)及び阪南港が・・・の・・・域に入るおそれが必至と判断された場合、あるいは両港が重大な影響を受けると判断された場合。 千葉港では、・・・に・・・域が達する前までに避難体制が完了することを目安に発令する。また、要嚮導船の※嚮導時間を考慮し、・・・前に作業が完了し安全に避泊できる時期に発令する。などと複雑だ。 ※嚮導時間=(要嚮導船/パイロット数)×・・・(時間) 講ずべき措置 直ちに港内、または港外の安全な場所に避難する。など概ね、・・・・・・・を勧める。(・・・制限もある。) その対象船は、 千葉港が・・・t以上(同入港制限)、京浜港や大阪港で・・・・t以上(同入港制限)。鹿島港 で、・・・・・DWT 以上の船舶は、原則として、・・・外へ避難すること。同・・・・・DWT 以上の・・・中の船舶は、速やかに・・・し、安全な・・・にて・・・すること。としている。また、徳山港では、船舶は直ちに港内または・・外の安全な場所に避難する。となっており、トン数に・・・してない。 解除時期 これら警戒体制の解除時期は、・・・の・・・・・外となったときや、強風域から出た時とされる。 |
|
|
|
上記の内容をフルスペックでご覧になりたい方は以下にてお願いします↓ |
|
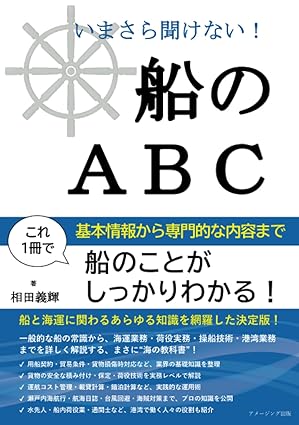 |
|