| 入港速度を計算する式がないではないが、風圧や、タグ、機関後進の制御力をトン数で計算しなければならないため、複雑で実用に適さないので、ここでは目安として記憶しやすい形の一例を記す。 (後進を引いて船を制御しやすい速力)
|
|||||||||||||||||
| 岸壁への接岸速度 岸壁前まできた後の接岸速度は、岸壁設計強度(・・・cm/secを想定していることが多い)以下となるように、・・・・・・cm/secで接近するのが理想とされている。 しかしながら、通常の速力・・・k’nt(・・・m/sec)で走っている際に風速・・・m/secを正横方向から受けた場合に・・・m/sec程度しか横圧されない船でも、速力が・・・k’nt(・・・m/sec)以下になると、・・・分で・・・m/secに達して横に流れてしまうというデータもある。 (大まかには、停止に近い速度の場合、船首が少し落とされた姿勢で流され、その圧流速度は風速の・・/・・程度になると言われている。) 岸壁まで・・・mに近づいた船が・・m/secで岸壁に近づいていくと、単純計算で岸壁正横まで・・分かかる。風速が・・m/sec下で、それは・・・m/secで岸壁方向に流されつつということになって、これでは接岸速度が過大である。速度が遅いと外力の影響を受けやすくもなるということですので、こういう際は、躊躇せず、タグをオーダーした方がよいということになります。 |
|||||||||||||||||
舵効き 舵はどこまで効くかという話だが、一般的に舵効きは舵面積、船速、舵角に比例する。これとは別にここでは風速の関連性について述べる。風速(m/sec)/ 船速(m/sec) が ・・・を超えると、相対風向が・・〜・・・°の広い範囲で、舵効きが非常に悪くなったり、または効かなくなる。従って、速力・・k’nt(・・・m/sec)で航行中の船でも、正横付近から風速・・m/seの風を受けると、保針が難しい。 ちなみにPilotの業務引き受け基準は風速・・m/sec以下になっているが、本船の船型、操縦性能、・・・・・・・、気象条件を判断し、船長は着岸可否やタグ使用を総合的に判断しなければならない。 バウスラスターは・・〜・・k’nt以下でしか使用できない限界があり、また・・・方向にしか効かず本船を斜めに引くことはできない。こういったところでタグが重用される。 接岸角度 DW・・・・・tぐらいまでの小型船では、岸壁との進入角・・〜・・°をもって接近し(アスターンをかけるや、アンカーを落として船尾を寄せる)、その後船首もやい(Spring)をとって接岸していくということが多かった。昔の教科書でもそういったことを書いていた。しかし、この方法は、行き足過大や、突風など外的影響が加わったときに岸壁との接触を招き易く、また、それらに対応もしにくい。 現代では、スラスターを持った船が大半であるし、接岸前にアンカーを落とす必要もあまりないことから、一旦、船腹の・・・倍程度距離をとって・・・・・に船を停め、その後、スラスターやタグで押して接岸させるという方法をとる船が多い。前述の着岸方法よりも若干時間を要すが、小型船であっても慎重な船長は平行着岸とすることが多い。 回頭域の広さに【本船の長さの・・・倍】を考慮 バウスラスター及びスターンスラスターの位置が、船の・・・から・・・・・にあって、同じ・・・で併用できた場合には、ほぼ・・・・・が可能である。ほぼと書いたのは船船首と船尾の構造が異なるので、実際には回頭中心がズレるから)しかし、タグボート1隻などで回す場合には、回頭重心が、力点から重心を隔てた反対側に移動するため、船の長さよりも大きな回頭径となります。これに風潮流の影響を加味し、船の長さの2倍以上を以って回頭域とするのが安全である。(水先人会ではバース前面での止むを得ない場合に限り、・・・Lを回頭基準としているようだ。) UKC(Under Keel Clearance) 余裕水深について。 P&Iクラブでは 港内航路 最大喫水の・・・% 港外航路 最大喫水の・・・% 外航航路 最大喫水の・・・% を推奨し、東京水先会では、本船の喫水に対する余裕水深は、下記の基準による。 1) 入出港水路において:喫水の・・・%以上を確保する。 2) 係留場所において、喫水・・m未満の船舶については・・・cm以上を確保する。喫水・・m以上・・m未満の船舶については、喫水の・・%以上を確保する。 などとなっているので、参考にしてほしい。・・・・・・・・・・による船体沈下は船底を流れる水の流速が増すと大きくなる着岸低速時の船体沈下量は一般に船の長さLppの・・ 〜・・2%とする)ので速力にも気を配り、Berth前は貨物の落下や土砂の蓄積、ゴミなどにより公称水深より浅いこともあるので注意願いたい。 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
関連ページ 離・着岸操船イメージ 上記の内容をフルスペックでご覧になりたい方は以下にてお願いします↓ |
|||||||||||||||||
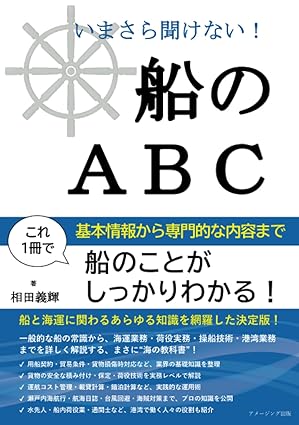 |
|||||||||||||||||
